忙しい毎日を送るビジネスパーソンにとって、「読書の時間がなかなか取れない」というのは、よくある悩みの1つではないでしょうか。
仕事に追われ、帰宅後も疲れて本を開く気になれない。とはいえ、知識のアップデートや自己成長のために読書は欠かせないよな…本読まないとなとは思っているんだけどなかなか読めないんだよな…そんなジレンマを抱えている方も多いはずです。
そんなあなたにこそおすすめしたいのが「耳読書」です。文字通り、“耳で読む” 読書スタイル。音声で本の内容を聴くことで、通勤中や家事をしながらといったスキマ時間を有効活用し、無理なく知識をインプットすることができます。
本記事では、耳読書がビジネスパーソンに最適な理由や、始め方、効果的な活用法までを詳しくご紹介します。忙しい日々の中でも学びを止めたくないと考えるあなたの、新しい習慣を始める第一歩となれば幸いです。
耳読書がビジネスパーソンに最適な3つの理由
耳読書がビジネスパーソンにぴったりな理由は、ただ「お手軽」というだけではありません。
ここでは、忙しい日常の中でも耳読書が効果的に機能する、3つの大きなメリットをご紹介します。
1)通勤・移動・運動・家事中に学べる

現代のビジネスパーソンの1日はとにかく忙しい。まとまった読書時間を確保するのは簡単ではありませんよね?
しかし耳読書なら、通勤中の電車や車内、料理や洗濯といった家事の合間、更にジョギング中やジムでの運動中など、“ながら時間” を活用しての “聴く読書” によって知識をインプットできます。
スマートフォンとイヤホンさえあれば、手も目も使わずに読書ができます。1日10〜20分でも積み重ねていけば、1週間で1冊以上の本を “聴く” ことは十分に可能です。これは、時間を有効活用したいビジネスパーソンにとって、大きなアドバンテージですよね。
特に私のおすすめは「移動中」に聴くことです。今まで移動中にスマホを見ていた人は、音声を聞いて、周囲を見回してみてください。今まで気づかなかったものが見えてくるはずです。
私が利用している電車から、富士山が見えるスポットがあるのですが、キレイな富士山が見える日も、車内では下を向いてスマホを見ている人がほとんどです。些細なことですが、富士山がキレイに見えた日は、気分がアップします。
耳読書は、知識のインプット以外にも、生活を豊かにしてくれるはずですよ。
2)目の疲れを防ぎ、集中力を維持できる

デスクワーク中心のビジネスパーソンにとって、目の酷使は日常茶飯事ですよね?仕事が終わった後、更に本を読むとなると、仕事でたまった目の疲れが集中力の妨げになり、なかなか読書が進まないと感じる方も少なくないでしょう。
耳読書であれば、視覚を使わずに情報を得ることができるため、脳の疲労感も少なく、よりリラックスした状態で、内容の理解に集中できます。
通勤中や就寝前など、目を使わずに、目を休めながらも、学ぶ時間をつくることができるのです。
3)記憶に残りやすく、インプットの効率が上がる

耳からのインプットは、音の抑揚や感情を伴って伝わるため、記憶に残りやすいという特長があります。
特に、ナレーターによる丁寧な朗読や、プロの声優による音声コンテンツは、聞き手の理解力や集中力を自然に引き出してくれます。自分好みの声や、好きな俳優さんが読んでくれたら、より集中力がキープされるでしょう。
さらに、音声による情報は反復再生がしやすいため、気になる部分を繰り返し聴いて、理解を深めることができます。これにより、ただ読んだだけでは得られない “定着力” が期待できるのです。
耳読書を始めるには?
耳読書は、特別な知識や機材、準備がなくても、すぐに始められるのが魅力です。
ここでは、耳読書を生活に取り入れるための基本的なステップと、より効果的に活用するためのポイントをご紹介します。
まずはアプリ選びから

耳読書を始める第一歩は、自分に合った「音声読書アプリ」を選ぶことです。代表的なサービスには、以下のようなものがあります。
- Audible(オーディブル):Amazonが提供する音声読書アプリ。プロのナレーターによる高品質な音声が特徴的で、ビジネス書や自己啓発系の本が充実しています。
- audiobook.jp:日本語のコンテンツが豊富で、月額料金もリーズナブルなため「ちょっと試してみるか」という方によって始めやすいのが特徴です。倍速の再生や一括購入にも対応しています。
- Google Play ブックス / Apple Books:特定の本のみ、音声読み上げに対応しています。本の購入費のみで使用が可能なのが特徴です。
最初は無料体験を活用して、聞きやすさや使いやすさ等、自分に合うかどうかをチェックしてみるのがおすすめです。
おすすめの耳読書ジャンル
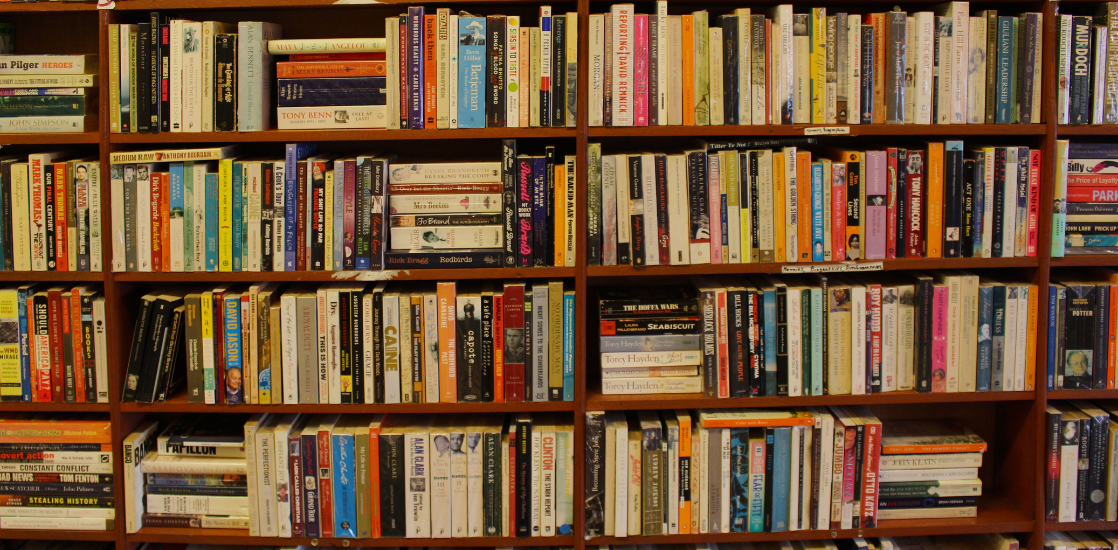
耳読書に向いているジャンルとしては、次のようなものが挙げられます。
- ビジネス書・自己啓発書:理論やノウハウを繰り返し聴くことで、理解を深めやすいです。
- 経営者の自伝・インタビュー:ナレーターの語り口調によって、感情移入がしやすく、内容が理解しやすくなります。
- 時事・ニュース解説:世の中の流れを把握しておきたいビジネスパーソンにピッタリです。
慣れないうちは、内容が重すぎない本や、上記以外のジャンルであっても自分がとても興味のあるジャンルから選んでみましょう。耳読書が習慣になってきたら、重めの本や、様々なジャンルにも手を伸ばしてみて下さい。
倍速再生の活用法&注意点
多くの耳読書アプリでは、1.25〜2倍速の再生機能が搭載されています。倍速再生を活用すれば、1冊を短時間で聴き終えることも可能ですが、慣れないうちは、早すぎる速度では内容が頭に入りにくくなります。
最初は1.25倍速からスタートし、自分の聞き取りやすいスピードを探って、調整しましょう。
また、集中力が落ちやすい時間帯や、初めて読む本、なんか内容が頭に入ってこないなと感じるときは、時短を優先せず、内容の理解を優先して、標準速度に戻すことも重要です。
聴いた内容の “アウトプット” で記憶に定着させる

耳読書でインプットした情報は、インプットしただけで終わらせず、アウトプットをすることで、記憶により定着しやすくなります。具体的には、以下のような方法を取り入れてみると良いでしょう。
- SNSや日記に、学びの要点や気づきをメモする
- 聴いた内容を、同僚や家族に話して伝える
- メモアプリに音声で感想を録音して残す
特に覚えておきたい箇所は、自分で朗読して録音し、それをまた後日聴くことで、しっかり頭に定着させる効果が期待できます。
本を読む際、黙読(声に出さずに読む)と音読(声に出して読む)では、異なる脳の領域が活性化し、特に言語の処理や記憶に関連する部分が、音読のほうが活性化することを報告している研究があります1。
“聴く→まとめる→伝える”の流れを習慣にすることで、耳読書が単なる情報収集ではなく、実践的な学びに変わりますよ。
“ながら聴き” は逆効果になることも

耳読書は「ながら時間」の活用に最適ですが、注意が分散しすぎると逆効果になることもあります。
たとえば、メールを打ちながら聴いたり、複雑な資料を作成しながら聴くと、内容がまったく頭に入らず、ただストレスになったり、作業の方も時間がかかってしまって、むしろ無駄な時間が増えてしまうことがあります。
耳読書をするおすすめの時間帯は「身体は動かしていても頭は自由な時間帯」を活用することです。通勤中の歩行や、ランニング、家事中など、脳の余白があるタイミングで聴くことで、効率よく作業もインプットも行うことができます。
まとめ
忙しい毎日の中でも、学びを止めたくない。そんなビジネスパーソンにとって、耳読書は強力で有効なツールとなります。
通勤や家事の合間に知識をインプットできるとともに、目の疲れを抑えつつ集中力も維持することが可能で、さらに聴覚を通じた情報は記憶に残りやすく、アウトプットと組み合わせることで実践的な学びにもつながります。
耳読書は、特別な準備がいらず、スマートフォンひとつで今日から始められる習慣です。小さなスキマ時間を積み重ねることで、確実にあなたの知識の幅と深さを広げてくれるはずです。
「読む時間がない」と感じている方こそ、ぜひこの新しい読書スタイルを取り入れてみてください。耳からのインプットが、あなたの毎日と未来をアップデートする第一歩になるでしょう。
参考文献・資料
- Miura N, Iwata K, Watanabe J, et al. Cortical activation during reading aloud of long sentences: fMRI study. Neuroreport. 2003;14(12):1563-1566. doi:10.1097/00001756-200308260-00004

