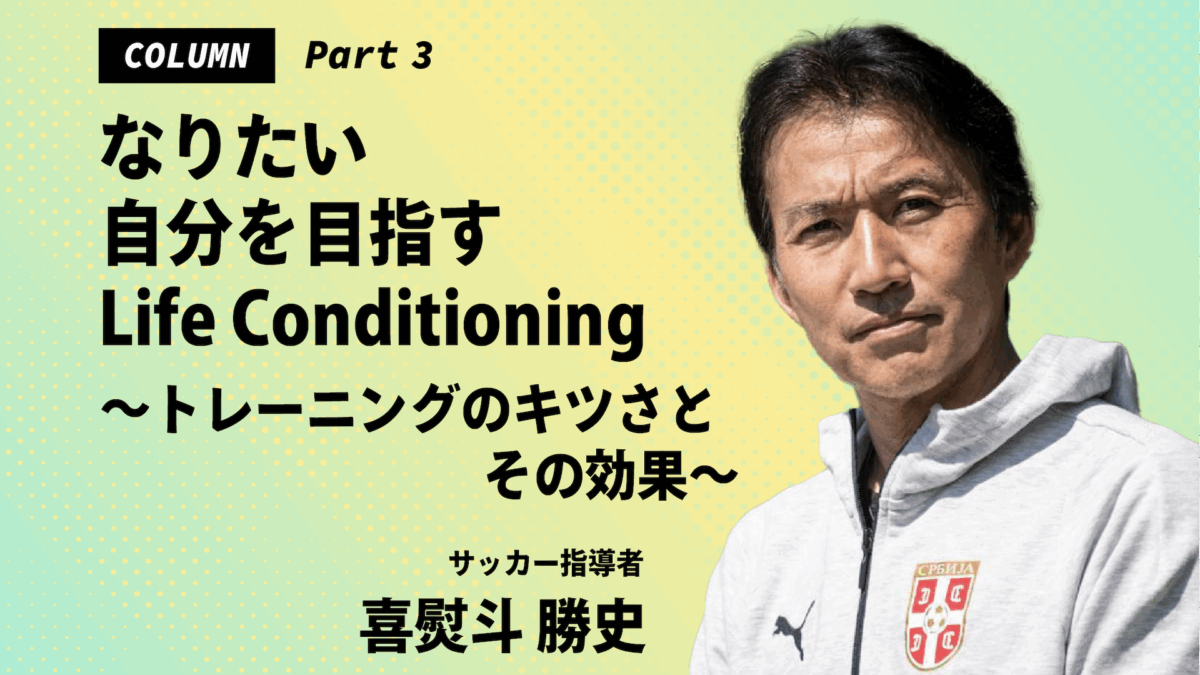「頑張ってるのに、なかなか効果が出ない…」そんなトレーニングの悩み、感じたことはありませんか?
第3回となる、喜熨斗勝史(きのし かつひと)さんのLife Conditioningコラムでは、日々の運動に “確かな成果” をもたらすためのヒントとして、「トレーニングのキツさとその効果」についてお話いただきました。
自分に合った “ちょうどいい負荷” とは? 継続できる頻度は? 国内外で活躍したプロコーチが、明日から実践できる具体的なアドバイスをお届けします。

喜熨斗 勝史(きのし かつひと / 1964年10月6日 生まれ)
- 日本サッカー協会公認S級コーチ(監督・コーチ・フィジカルコーチ)
日本のサッカー指導者。東京都練馬区出身。日本体育大学、東京大学大学院修了。Jリーグでトップチームのコーチを歴任したのち、中国スーパーリーグに移籍した。2016年から、中国スーパーリーグでは唯一の日本人コーチ。語学力を活かし、グラウンドでは英語、ポルトガル語での指導もできる。
トレーニングの「負荷」の設定の仕方について

こんにちは。最近、朝晩は寒さが身に染みるようになってきましたね。手袋なしでは、手先も冷えるようになってきました。
ただ、寒いからと言って、運動量を落としてしまっては、「巣籠り太り」に拍車がかかってしまいます。トレーニングを、外でのランニングから、自宅でのヨガやピラティスなどに切り替えられるといいですね。トレーニングのチャンスを逃さないように、頑張っていきましょう。
ただ、トレーニングと言っても、その「負荷」をどのように設定すればいいのかは、難しい問題です。ただの「足踏み」や「ストレッチ」のような小さな負荷から、腕立て伏せをこれ以上できなくなるまで反復したり、バーベルを何回も持ち上げたりするなどの重い負荷まで、その強度は様々です。
普段、運動をしていないのに、いきなり「Boot Camp」のようなハードなトレーニングをやると、次の日には「激しい筋肉痛」に襲われてしまいます。その結果「体が痛くて逆に運動できなくなっちゃう」「生活活動するのもしんどい」なんてことになりかねません。
ライフコンディションを向上させるためには、トレーニングの負荷は正しくコントロールすることが大切なのです。厳密には、諸説様々ありますが、今回は、このトレーニング負荷を3つに分けて考えてみましょう。
1)~33%/MAX のトレーニング負荷

まずは「33%/MAX以下」のトレーニングについてです。これは、皆さんが持っている「最大努力の33%以下の負荷」という意味です。
例を挙げると、100kgのバーベルを持ち上げられる人なら、33kg以下の重さを使ったトレーニングを行うこと、という意味になります。
しかし、アスリートならまだしも、一般の人たちが “最大努力” の値を知っている人は少ないはずです。そんなときは、まさにあなたの「感覚」が頼りになります。
運動をしていても「まだ余裕があるな。楽だな」くらいの感覚が、この “最大努力の33%以下の負荷” だと思ってください。この負荷なら、しばらく動いても、そんなに苦にならないし、次の日に筋肉痛や疲労が残ることはありません。
つまり、皆さんの日常生活は、ほとんどがこの中に入ってしまいます。非常に軽い負荷ですが、何もしない(出勤しても椅子に座りっぱなしであったり、1日中在宅ワークをしていたり)よりはマシです。
積極的に歩いたり、階段を上ったり、ちょっとストレッチをするなどして体を動かしましょう。1回の運動はできれば5分以上。スキマ時間に組み込んでみてもいいかもしれませんね。
ただ、この負荷のトレーニングは簡単にできて、疲れが残らない代わりに、能力や筋力を向上させるには不十分です。
疲労がたまったときのリカバリートレーニングに使われることもありますが、やはり、最低限の代謝能力や運動不足を解消するレベルだと思ってください。
アグレッシブにライフコンディションを向上させるには、これだけではちょっと物足りませんね。
2)33~66%/MAX のトレーニング負荷

この負荷が、まさに皆さんのライフコンディションをアグレッシブに維持していくために必要なレベルと考えます。
33~66%と書きましたが、一般的には「50%前後」と考えてください。トレーニングしたらちょっと疲れる、ちょっと汗ばむ(汗をかく)感じのレベルです。
ランニングなら「20~30分程度」、筋トレなら「ちょっと筋肉が張るレベル」になります。
毎日続けても大丈夫ですが、このレベルのトレーニングは週に2回から始めることをお勧めします。トレーニングに慣れてきたら、回数や時間を増やしても大丈夫ですが、初心者にはキツさが残るかもしれません。
また、このレベルからは、マシンやチューブといったいわゆる「トレーニンググッズ」や、テニスやフットサルなどの「競技性」が必要になってくるのも特徴の一つです。
非常に心地のよいトレーニングですが、やりすぎたり、義務感が強すぎたりすると、怪我や過労につながってしまうので気をつけましょう。楽しみながら取り組むのが、長続きさせつつもトレーニング効果をあげるコツです。
3)66~100%/MAX のトレーニング

このレベルのトレーニングはビルドアップ(=より高めていくこと)を目指すものになります。
筋肉を大きくしたり、心肺機能を向上させたりするのに必要なトレーニングです。当然、疲労は溜まるし、怪我やスポーツ障害の危険性も高まります。
プロやアマチュアを含めたアスリートは、このレベルのトレーニングを繰り返すわけですが、身体にかかるストレスも増すので、コーチやトレーナーによるコントロールが重要になってきます。
健康の促進が主な目的となる、一般のスポーツ愛好家の皆さんは、このレベルでの運動は「週に1~2回」で十分です。他のトレーニングと組み合わせるならば、週に1回でも大きな効果が出てくるはずです。
やみくもに厳しいトレーニングをするのではなく、合理的かつ理論的にプログラムを作ってチャレンジしてみてください。最近では、フィットネス系のアプリに自分のフィットネスレベルを設定すれば、効果的な強度を設定してくれるものを多いです。
継続することができれば、あなたもアスリートのように引き締まった身体になるはずです。
まとめ
さて、今日はトレーニングを行うときの負荷について、お話をしました。
でも実は、大切なのは、どのように色々なトレーニングを「組み合わせるか」なのです。筋トレと有酸素。きついトレーニングと軽いトレーニング。上半身と下半身。など、その組み合わせ方は様々です。
そこで、次回はその組み合わせ方をいくつか紹介します。コロナ禍で、在宅ワークが増える中、トレーニングバリエーションを豊富にして、この冬を乗り切りましょう。
ピンチをチャンスに変える。身体と心を元気にして、2021年は笑顔の多い年にしたいですね。
KINOSHI
編集後記
自宅でトレーニングをすると、どの位の頻度で、どの位の強度でやったらよいのか分からないまま続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
せっかく時間を作ってやるトレーニングなので、今回の記事を参考に効果的なトレーニングにして頂ければと思います。体づくりだけでなく、毎日を笑顔で過ごす為のLife Conditioningとしてトレーニングを取り入れていきたいですね!
カズのコーチが語る “続く運動” のヒントとは?
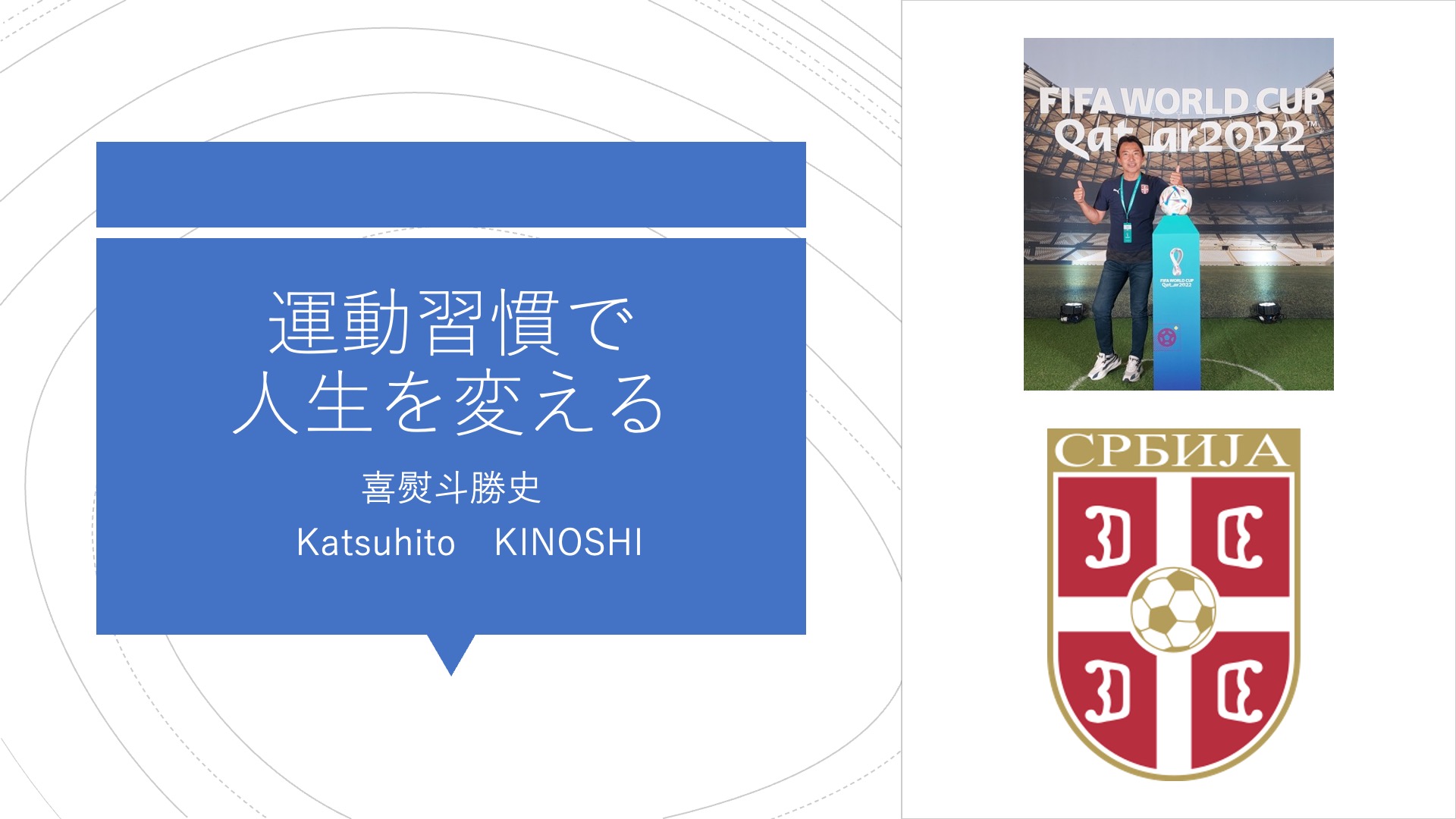
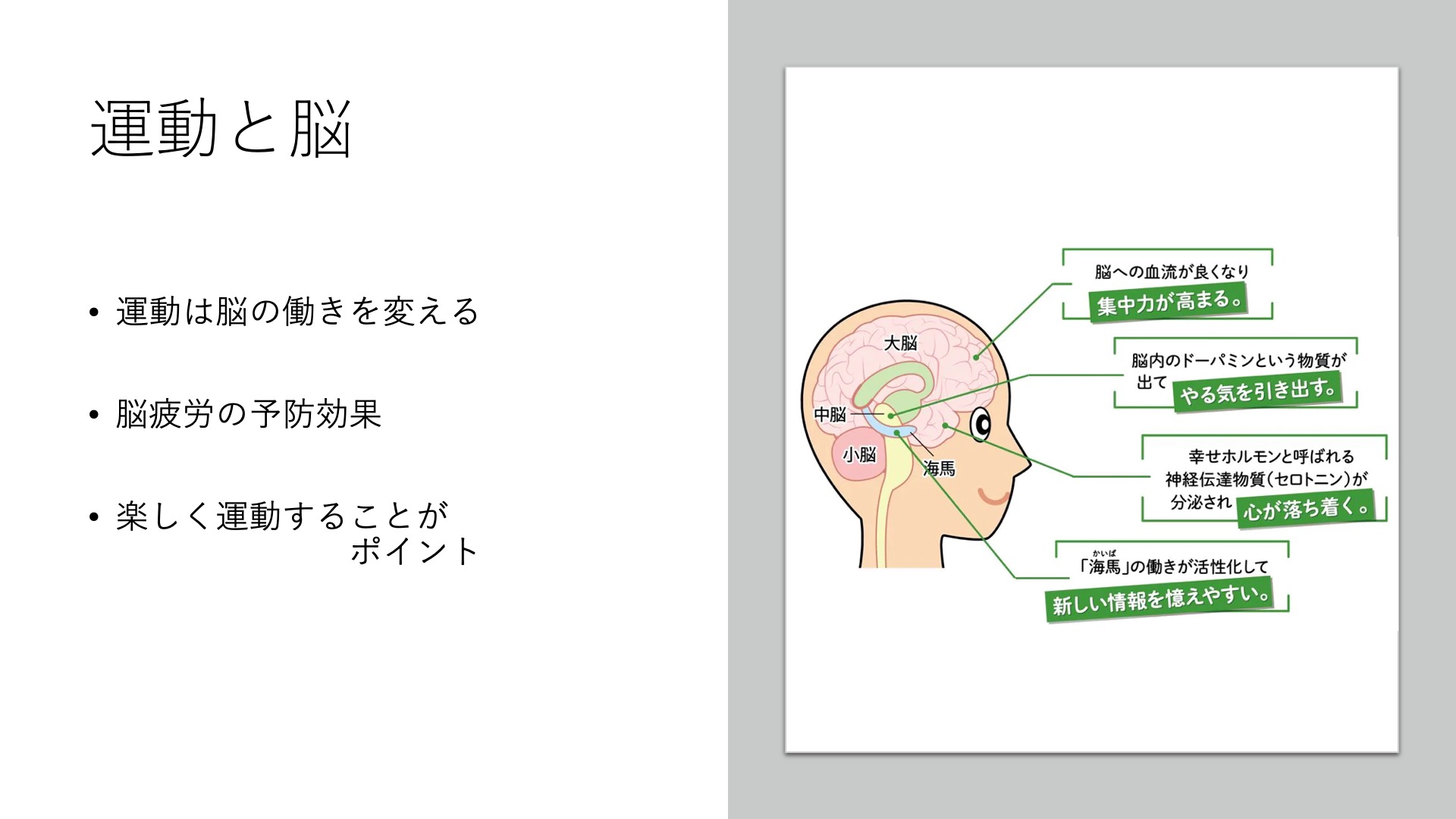
「運動が大事なのはわかっている。でも、続かない。」
そんな声に向き合ってきたのが、プロサッカーコーチの喜熨斗勝史(きのし かつひと)氏。
三浦知良選手のパーソナルコーチとして30年以上にわたり、
トップアスリートの“継続力”を支えてきた専門家です。
喜熨斗氏が提供する企業向け運動セミナー「運動習慣で人生を変える」では、
企業で働く方々に向けて、運動を“続けたくなる”ための心と体の整え方を、
豊富な経験と具体例でわかりやすくお伝えします。
▶ 健康経営の施策として何か始めたい
▶ 運動習慣のきっかけを社員に届けたい
▶ モチベーションより“仕組み”で続ける方法を知りたい
そんな企業ご担当者様におすすめの講演です。まずはお気軽にご相談ください。