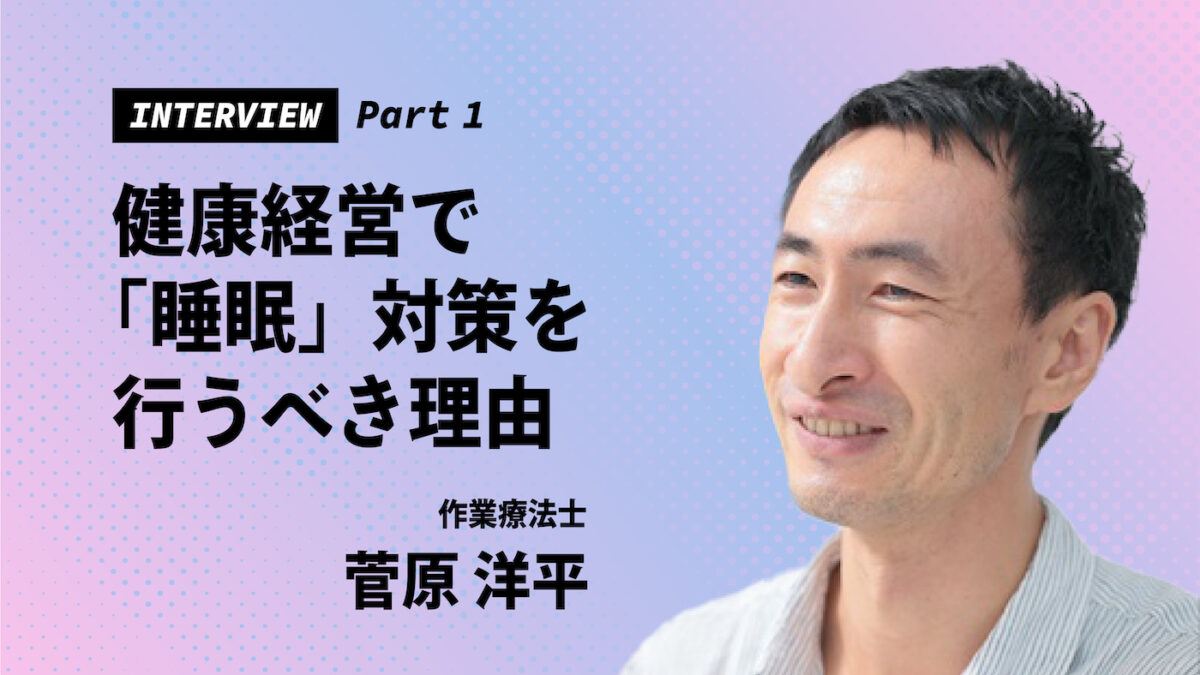現代のビジネスシーンで注目されている「健康経営」。これは従業員の健康を経営の中心に据える考え方で、ここ数年で非常に多くの企業が取り組み始めています。
中でも特に重要視されているのが、従業員の「睡眠」です。なぜ健康経営において、睡眠対策がこれほどまでにキーとなるのでしょうか。
今回、企業のパフォーマンスにおいて従業員の睡眠がなぜ重要なのか?というテーマについて深く探るべく、作業療法士であり、企業に向けた「睡眠・健康」に関するコンサルティング業・講演等でご活躍されている菅原洋平氏にインタビューを実施しました。
菅原先生の見解を通じて、健康経営と睡眠の深い関連性に迫るとともに、具体的な睡眠対策の重要性を明らかにしていくインタビュー連載の第1回です。
- 第1回 健康経営で「睡眠」対策を行うべき理由 ← 今回の記事はこちら
- 第2回 健康経営/睡眠対策の成功事例をご紹介!
- 第3回 社員の睡眠を守るための睡眠の質向上策
- 第4回 季節に合わせた対策で最高の睡眠を
- 第5回 良い睡眠のために運動をオススメする理由
第1回目となる今回は、健康経営の中で企業が睡眠対策に取り組む際、ポイントとなる成功の秘訣をお伺いしました。
なぜビジネスパーソンにとって睡眠が大切なのか?

編集部:
睡眠が大切だという事は何となく分かっていても、睡眠を削って夜間仕事をしたり、夜遅くまでネットサーフィンをしている人が多いのも実情だと思います。
今改めて、睡眠が何故ビジネスパーソンにとって大切なのか?について先生のお考えをお話いただけますか?
菅原先生:
企業の中で睡眠に取り組む場合は、まずはその意義を、社員の皆さんに伝える事が大切です。
睡眠はプライベートな話なので「寝なくても本人の自由」といった風潮もあり、健康経営にしろ、働き方改革にしろ、企業内で睡眠に取り組む際は、「睡眠」の価値観を一方向に定めないと、「別に寝なくても自由」なので、「不健康な生活をする権利」などといった話も出てしまいます。
企業として何故取り組むのか?が明確でないと行動変容に至らないんですね。
【事故を起こさない】【売上を上げる】【生産性を上げる】など、社員の皆さまが共通して目指している事に対して「睡眠が有効だ」と位置づけられる事で、初めて「睡眠」が自分の仕事の一環としてとらえる事が出来ます。
健康経営として取り組む際も、健康になる事が目的ではなく、「生産性や業績を上げていく」という事が目的になるので、睡眠の情報を発信する際に「健康になる為の睡眠」とは位置付けず、「生産性向上・業績を上げる為の睡眠」と明確に打ち出して頂くようにしています。
編集部:
皆さんのプライベートが充実しますよ!というよりも、いかに仕事と繋がっているか?という事を明確に打ち出す事で取り組みが成功するかどうか?が変わってくるのですね。
菅原先生:
そうですね。結果的にアンケートを取ってみたら「休日が充実しました」という回答が出てくるのが一番良い例だと思います。企業から「休日を充実させましょう!日々を楽しく過ごしましょう」など発信しても、そんなの「余計なお世話だ!」となってしまいます。
そういったスタンスを前に出すのではなく、「会社が自分にとって利益のある情報を提供してくれたから、会社にも自分がそれを還元したいな」というワークエンゲージメントを生み出していく為に、会社が発信するメッセージは、結果的に「会社のおかげで人生が豊かになりました」と言ってもらえるような情報を発信していくことが大切だと思います。
仕事の生産性アップや事故防止に「睡眠」が重要な理由

編集部:
企業が健康経営の一環として「睡眠」にアプローチするにあたって、「仕事の生産性」や「事故を防ぐ」という所が伝えるべきキーワードになるという事ですが、この目的に絞った場合、睡眠は脳や体に対してどのような影響があると思われますか?
菅原先生:
脳がちゃんと働いているか?という事は基本的に自分では分からない事です。皆さんが判断基準にしていることが多いのは「眠くないならまだやれる」という感覚かもしれません。
眠気がなければ、集中できている。
眠くなってきたら、集中できていない。
という判断されるのですが、眠気というのはもっと前の段階からきています。
例えば、脳は眠くなってくると「マイクロサッケード(急速な眼球運動)」といって、目のキョロキョロとした動きが対象の範囲外まで動くようになるので、「気が散る」という感覚が出てきます。この気が散った時点で脳はもう寝ています。
気が散り始めた段階で「脳はもうここで活動限界ですよ」という事が示されていると気が付く事ができれば、「気が散ったまま一日中過ごしてしまった」という生産性の低い状態を生むのではなく、
気が散りだしたという事は、もう眠いのかもしれないな。
脳をメンテナンスする必要があるからちょっと席を立って目を閉じてみるか。
みたいな感じで、個人が策を講じる事で、会社の生産性を維持する事が出来ますよね。
これは、生産性を向上させるというよりは「もともとは高いはずの生産性を、誤った働き方や誤った認識によって下げてしまう行動を防ぎましょう」という事なんですよ。
なぜ、生産性を下げる事をあえてやってしまうかというと「脳の仕組みを知らないから」です。これは習わないからだけの話なので個人のせいではありません。個人の性格でもありません。脳の性質だからです。
という風に、あくまでもジェネラルな、皆に共通する事項であるという風に引き上げて伝える事で、社員の方からは「救われました」とか言われる事もあります。
精神論から切り離して考えることを最初に伝え、脳の仕組みを知る機会を会社で提供しませんか?という事です。
その機会を提供したら、「脳の性質を理解して生産性の高い仕事をする事」をビジネススキルとして活用していきませんか?という提案です。
スキルが高まれば当然皆さん出来る事なので、「生産性が上がらないのは個人のせいではありませんよ」というメッセージが伝わっていくという構造を生み出していく事が狙いです。
実はささいなことが睡眠不足のサインの可能性がある

編集部:
抽象的に「生産性を上げましょう」とか「効率的に」と言われても、どうすれば良いのか分かりづらいですが、「気が散る」「眠気」といったサインが脳の活動限界だと知っていれば、対策できますよね。尚且つ個人レベルでチェックが出来て対処法がわかっていれば、行動を起こすきっかけになるんですね。
菅原先生:
セルフチェックのポイントをお伝えする事はとても大切だと考えています。
例えば「飴をなめている時にかんでいたら寝不足ですよ」とか「話している時にアクセサリーやネクタイを触っていたら寝不足のサインです」など、思いもよらないような所から、脳は実は活動限界のサインを出しています。
そこで早めに気づくことが出来れば早くリカバー出来てローコストですよね。放置しておけば、それだけリカバーするのに時間がかかるし、コストもかかるので、早めにチェックした方が良いのではないですか?といって、チェックしてもらいます。
「こんな些細な事も睡眠不足のサインなのであれば、私も睡眠足りていないのかも!」と当事者意識を持ってもらうという事が、皆さんにとっては引っかかりやすい流れなんだと思いますね。
編集部:
興味を惹く意外なチェック項目を企業内で打ち出して、「自分も実はそうかも!」と思ってもらう事が啓発の第一歩なんですね。
菅原先生:
そうですね。「自分がそうかも!と思ったら睡眠を見直そう」ではなくて「自分がそうかも!と思った事が、仕事にリスクを生んでいるかもしれませんよ」というのが企業側からのメッセージです。
「ほら!こんなに当てはまっているじゃないか!寝不足は悪いんだぞ!」と責めるのではなく、「安全な業務を行う為に、皆さんが自分の事をチェックできるポイントを活用しましょう」という形で、個人の生活スタイルが悪いからではなく、業務の為にチェックするべきポイントです。と発信するメッセージを一貫させるという事が大事ですね。
あとがき
「何となく気が散って仕事に集中できない」という問題は誰しも一度は経験した事があるお悩みなのではないでしょうか?
これは、個人の性格の問題でもなく、気合が足りないからでもない。脳の性質を理解する事で、仕事の生産性を高める事が出来るのであれば、プライベートな問題だと思われがちな「睡眠課題」も皆さんに興味を持って取り組んでいただけそうですね。
次回は、健康経営に取り組む企業が「睡眠課題」に取り組んだ【成功事例】を、ポイントを解説しながらお伺いします。どうぞお楽しみに!
【お問合せ】
睡眠・休養・作業療法等のプロフェッショナル!
菅原洋平先生の講演・ワークショップ依頼はこちらからお問合せください。
※オンライン対応可能
【プロフィール】
菅原洋平
作業療法士。ユークロニア株式会社代表。
アクティブスリープ指導士養成講座主催。
国際医療福祉大学卒。
国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事したのち、
現在は、ベスリクリニック(東京都千代田区)で薬に頼らない睡眠外来を担当するかたわら、生体リズムや脳の仕組みを活用した企業研修を全国で行う。
その活動はテレビや雑誌などでも注目を集める。
主な著書に、13万部を超えるベストセラー「あなたの人生を変える睡眠の法則」、12万部突破の「すぐやる!行動力を高める科学的な法則」など多数。