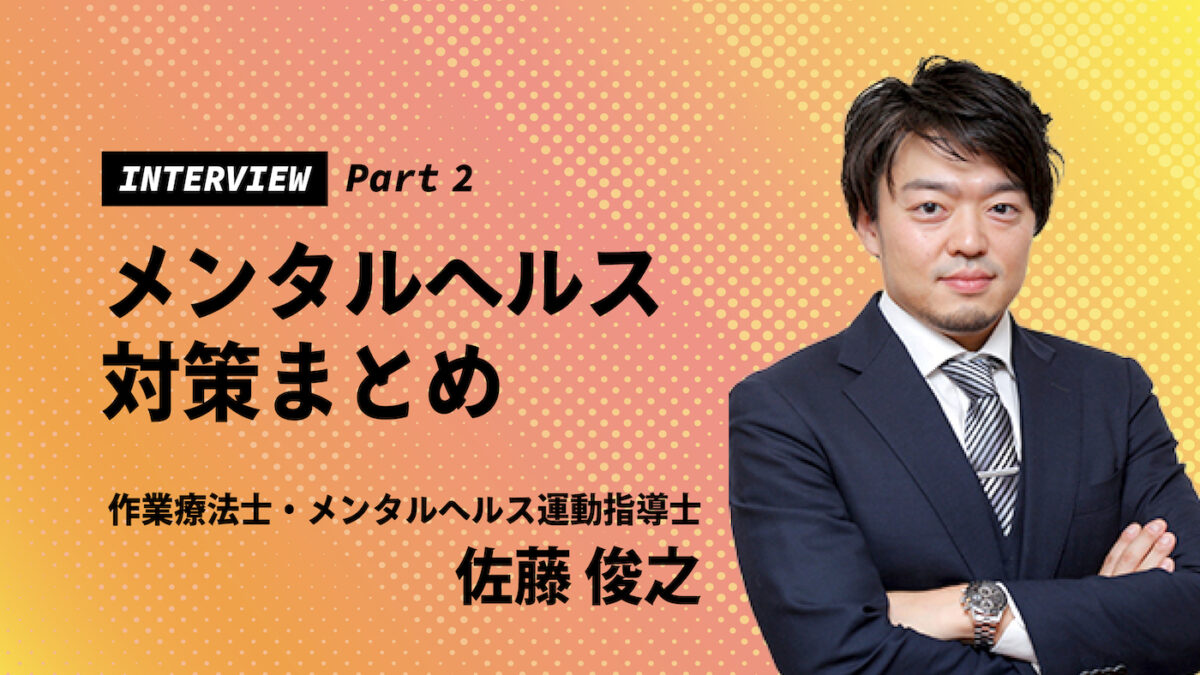精神科作業療法士、佐藤俊之さんへのインタビューPart2です。
今回は、メンタルヘルス対策として、個人でできることはもちろん、企業として取り組むべきことについてご紹介します。
Part 1の記事は「【佐藤俊之氏インタビュー①】運動がメンタル不調に効く理由」からご覧ください。
メンタルヘルス対策としてまずは「運動」を取り入れる

編集部:
メンタル不調を予防する、オススメのライフスタイルについてお聞かせください。
佐藤さん:
まず第一に運動は入れていただきたいです。
厚生労働省が提示した「健康づくりのための身体活動基準20131」では、18歳~64歳の方の場合、スポーツや体力づくりで体を動かす量として、「強度が3METS以上の身体活動を23エクササイズ行う」と基準を定めています。
これは「息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う」事に相当します。
編集部:
そういった運動をメンタル不調予防として取り組む際、一人で始める・一人で続けるというのはなかなかハードルが高そうですね。
佐藤さん:
企業として、メンタルヘルス対策として運動を取り入れるためには、昭和的になってしまいますが、会社で部署対抗の運動会など、何か運動せざるを得ない状況を作る事ですかね。会社の中で企画として何かできると良いと思います。
編集部:
競技スポーツが出来るコミュニティーを自ら探すのはハードルが高いので、共通点がある仲間同士で体を動かせる場があると良いですね。
佐藤さん:
そうですね。多くの方は自ら仲間を募るという所がハードルになると思うので、会社として企画があったり、補助があるというのが助けになると思います。
今はSNSやZOOMを使ったイベント等、コロナ前より知らない人や、距離的に離れている人とも気軽に繋がれる時代になっているので、それを上手く活用して、共通の趣味を持った人と繋がってイベント等に参加出来れば、生活にハリが出たり、会社以外の居場所が出来るのでおすすめです。
運動に限らず「仲間」が見つけやすくなったのは、コロナ禍の利点ではないでしょうか?
メンタル不調の予防には「生活リズムの安定」が重要

佐藤さん:
また、予防といった観点では「生活リズムを安定させる事」が重要です。これはもちろん出社している方、リモートワーカーの方も共通で「就寝時間と起床時間を毎日固定化する」事が何より大切です。
ソーシャルジェットラグという言葉もある通り、人間は自分自身で時差を作ってしまう動物なので、夜更かしをしたり、休日に寝だめをしたり、更にリモートワークだとリズムがずれやすく「いつでも寝れて、ムクって起きてすぐパソコンを立ち上げて仕事をしちゃう」といった事も珍しくない様で、常に時差ボケの様な状態になってしまいます。
生活リズムを整える際はまず、太陽の光を浴びて体内時計をしっかりと働かせる事、日中は運動を取り入れ、寝る時間と起きる時間は常に安定させることですね。特に土日の様に連休がある方は「金曜日の過ごし方」というのが大事になります。
編集部:
なぜ、特に「金曜日」なのでしょうか?
佐藤さん:
「ブルーマンデー症候群」という言葉があります。これはただ単に「月曜日は少し気分が下がって仕事が憂鬱になるだけ」と侮ることは出来ず、ある研究によると「月曜日の自殺者数は土曜日の約1.5倍以上だった」というデータもあります。
金曜日、いつもどおり過ごす事が重要なのですが、どうしても私達は金曜日にストレスを解消したいもので、夜ふかしをしたり、お酒飲んだりして土曜日の朝起きられなくなり、日曜日までダラダラとリズムがずれたまま過ごしてしまい、月曜日の出社が辛くなってしまいます。
生活リズムを考える際は、特に金曜日の夜から始まる「休みの過ごし方」に気をつけましょう、というお話をしています。
生活リズムを整える上で重要な睡眠について、ぜひ「寝付きが悪い人必読!寝付きが良くなる6つの入眠スイッチ」の記事も参考にしていただけたらと思います。
メンタルヘルス対策として知っておくべき「不調のサイン」

編集部:
メンタル不調にいち早く気づく為の「サイン」の様なものはありますか?
佐藤さん:
サインとして重要なのが「今まで楽しめていた事が楽しくなくなってしまった」という状態です。テレビでも何でもいいのですが、趣味が全然楽しくない、もしくは趣味自体にやるのが億劫となるというのは、メンタル不調の大きなサインだと思います。
その他のサインとして重要なのは「自分の周りの人」ですね。本人は気づいていない段階で、周りの人が先に気づく場合もあったりするので、表情や、挨拶の反応がいつも遅い、服装や髪型の変化、寝すぎているなどに周りが先に気づくパターンもあります。
編集部:
会社や家庭の中でメンタル不調を予防する為には、周りの人が異変に気づけるというのが、重要になるのですね。
佐藤さん:
そうですね。雑談が全然雑じゃないってことですね。
「今日、何か元気ないね」と言える関係や、「今日ちょっと調子悪いから手伝ってくれない?」みたいな事をどれぐらいラクに言えるか?というのが大切になると思います。
編集部:
そうなると、コロナ禍のリモートワーク推進で、直接顔を合わせる機会が減って、コミュニケーションの機会が失われている場合は要注意ですね。
佐藤さん:
そうですね。企業のメンタルヘルス対策としてできることは、コロナ前にあった様な「雑談」が出来る時間を、意識的に作る必要があると思います。「会議の冒頭10分は仕事の話はしない」と決めて、コミュニケーションの時間を確保している企業さんもある様です。
メンタル不調を引き起こす原因
編集部:
メンタル不調の原因は様々あると思いますが、コロナ禍になってから「不調の原因」にも変化はみられるのでしょうか?
佐藤さん:
これは復職された方から良く出る声なのですが、状況が変化し続けている中、復職してみたら「コロナ対応」を求められて、環境の変化についていけないというお悩みが多く聞かれます。
テレワークの対応なども、復職したばかりの方はリモート不可で出社しなければならない。といった様な事例もあって、会社が変化についていけていない場合、そこの歪みがどうしても病気を持っていたり、休職経験があるなどの弱い立場の方にきていて、辛くなってしまう。という事態は散見しますね。
また、リモートワークで気軽にコミュニケーションが取れなくなっている場合、わざわざメールにしてまで相談するのは億劫だったり、オンライン会議の中、他の人の手を止めてまで相談する勇気は出なかったりで、どんどん自分を追い込んでしまって、うつ病の発症・休職の状態にまでなってしまう、という事は多いにあります。これはリモートワークの弊害ですね。
リモートワークを推奨している企業は、この辺の気持ちや事情をしっかりと汲んで、メンタルヘルス対策を考える必要があると思います。
編集部: 先ほどの「サイン」のお話にもあった様に、今は周りの人が異変に気付きにくい環境にあるという事を意識しなければならないですね。
佐藤さん:
普段やっていたコミュニケーションをしっかり分析して、それに相当するような時間をオンラインでも作る様にする工夫が必要ですね。
リモートワークの場合、特に一人暮らしの方は大変だと思います。「そういえば今日誰とも喋っていなかった」とか、オンラインミーティングも全てカメラオフとルールで決まっている企業さんもあるので、そうなってくると着替える理由さえ無くなってきてしまって、生活自体のメリハリが無くなってしまいますよね。
コロナ禍の運動不足・コミュニケーション不足によるメンタル不調を防ぐ為にも、うちのリワークプログラムの様に、運動をきっかけにコミュニティーを作っていけると、体も動かせるしコミュニケーションの場も確保出来てメリットが大きいと思います。
リモートワークはメンタルにとってメリットもある

編集部:
コロナ禍でリモートワークが推奨され始めてもう2年以上経ちましたが、今後更にリモートワークの弊害が顕著になり、メンタル不調を抱える方が更に増えてくるのでしょうか?
佐藤さん:
先ほどお話した様に、確かにリモートワークによる弊害もありますが、実際の所はリモートワークになって助かった人達もいらっしゃいます。
人間関係が辛かった人は適度な距離感が生まれたり、通勤や電車がストレスだった方々にとっても負担が減っているので、リモートワークもデメリットばかりでは無いと思います。
リモートワークになった事で精神的・体力的負担が減って、職場の人との人間関係から少し解放され、家でも仕事が出来るので所属している感覚は得られる。といった形で、リモートで助かっている人も一定数いるのは事実だと思っています。
コロナ禍の働き方も悪い事ばかりではないので、これからは、個人のコンディションに合わせて、リモートや通勤、その割合など柔軟に選べる働き方が理想ではないでしょうか。リワークからの復職の場合、出勤日数も徐々に増やしていく等の対応をして頂けると、復職もかなりスムーズになります。
編集部:
コロナ禍の多様な働き方を上手く活用して、メンタル不調に陥る方が少しでも減ると良いですね。
佐藤さん:
リワークプログラム内で運動を提供する際、私達は「どうやってチームに貢献するか」という事をメンバーさんに考えて頂いています。何もプレーだけでなく、マネージャー的な動きとか、監督とか、審判とか、運動プログラムにどうやって自分が参加していくかというのは、様々な方法があるはずです。
実際、今度フットサルの審判をやってくれる方は、ケガをしているのですが「その間もちゃんと自分なりに貢献したい」という事で、自ら審判を申し出てくれました。
会社の中でもこの様な形で、人それぞれ得手不得手やコンディションの差はあるけれど、広い視野を持って自分には何ができるか?皆がチームに参加して仕事をするにはどの様な働き方・割り振りが良いのか?が考えられると、メンタル不調に陥る方は減って来るのではと思います。
編集部:
貴重なお話をありがとうございました!
あとがき
今回のお話の中では、コロナ禍の弊害と逆に選択肢が増えた事での利点など、様々な観点からお話を伺いました。
個人が出来る工夫としては、リモート・通勤共通で「生活リズムを整える事」を実践しつつ、職場に限らず運動やその他の趣味で繋がれる「居場所」を意識的に作って生活にハリを保ち、職場でもオンラインでも、自分がやりやすい方法で生活に「運動」を取り入れる。
会社としては、何気ないコミュニケーション(雑談)が不足しない様、気軽に声を掛けられる環境を作り、不調の変化に気づける・気づいてもらえる様にする事。
そして、個人としても会社としても、どの様な働き方が良いのか?個人がそれぞれどういったやり方で貢献できるのか?広い視野を持って選択出来る環境が、これからの時代Well-beingな働き方として勧められそうです。
参考文献・資料
- 「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」について |報道発表資料|厚生労働省. www.mhlw.go.jp. Accessed July 26, 2023. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple.html
【プロフィール】
佐藤 俊之(さとう としゆき)
■所属:医療法社団柏水会三軒茶屋診療所 東京リワークセンター/慶應義塾大学病院/アームズラボ
■資格:作業療法士/精神保健福祉士/公認心理師/一般社団法人日本うつ病リワーク協会認定/リワーク認定スタッフ/日本作業療法士協会 認定作業療法士(AOT)/一般社団法人SST普及協会 認定講師(NO97)/日本心理教育・家族教室ネットワーク認定 家族心理教育インストラクター/WRAPファシリテーター/日本スポーツ精神医学会認定 メンタルヘルス運動指導士/ストレスチェック実施者